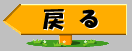治水行政の民主化を進めよう
〜「脱ダム」の むこうへ〜
地域教育研究会 伊藤貞彦
|
(一) |
田中長野県知事が「脱ダム宣言」を発したのは2001年2月であった。この衝撃的な宣言は、まさに全国を駆け抜けたといってよい。
あれから4年。いま、長野県はダムなし治水の「長野モデル」を創出するために、苦闘している。苦闘の要因は、ダム計画の基礎となっている基本高水を前提としていることにある。
基本高水とは、治水計画において、一定の確率で想定される治水基準点での最大流量のことで、これからその地点の最大通水能力に見合った流量を差し引いた残りが洪水調節の流量とされている。
そこで、ダム計画を含む治水案の基本高水を前提として、ダムなし治水案を考えようとすると、ダムで調整を予定していた大量の洪水流量を他の方法で引き受けなければならなくなり、極めて困難な課題に直面する。浚渫や堤防のかさ上げ、川幅を広げる引堤や、上流山地の保水力強化などでは、引き受けられる流量はそれほど巨大ではないからである。
さりとて、いったん表示された基本高水を引き下げることには、当然のことながら流域住民も関係市町村長や議会も大いに危惧を抱いてくる。というのはいざ洪水被害が出た場合、その被害を蒙るのは、流域住民や関係市町村長・議会であるからで、その意味では、実は基本高水は高ければ高いほどよいということにもなる。
しかしそうした考えを採れば、川の両岸に万里の長城のような高い護岸をつくるか、自らの居住地の上部により巨大なダムをつくれば安心というところに行き着くであろう。もちろんダムも護岸も決して老朽化も破損もしないという前提の上でである。
とはいえ、そうなると、川は人間の生活から完全に遮断され、流域の人々は長大な護岸やダムの破損を心配しつつ日々を送るということになるであろう。つまり、生活から川の恵みも水辺の潤いも失って、いわば人工の城壁に守られた生活というわけである。よもや、これが理想とは誰もいわないであろう。
|
(ニ) |
ではどうすればよいであろうか。それは、治水計画の基本高水が本当に妥当なものであるかどうか、検証しなおしてみることである。
その問題が、いまや時代の要請でもあることをみるために、わが国の治水の推移をざっと振り返ってみたい。
明治29年(1896)に制定された河川法は、主要河川の管理は国が行うという体制を確立した。そのことによって治水費は税によって賄われることとなったが、流域住民は河川管理から締め出されることとなったのである。
その後、同法は昭和39年(1964)に改正されたが、ここでも治水計画に流域住民は与り知らない存在とされ、慣行水利権に対して許可水利権が大きく拡張された。そこで、それに応えるために水資源開発と大規模治水事業が推し進められ、河川環境の大破壊が行われてきたのであった。
昭和46年(1971)には「河川管理施設等構造令」が定められ、治水構造物についての建造基準が明示された。これは事実上国の治水費支出における施設基準とされてきた。
ところが、その後環境問題が大きく叫ばれるようになり、46年環境庁が発足、平成4年(1992)地球サミット、平成5年(1993)環境基本法、生物多様性条約批准と続く。こうした中で建設省(当時)も平成2年(1990)「多自然型川づくり要領」を出し、第10次治水5か年計画策定にあたっては、できる限りのコンクリート構造物の廃止を謳った。
そして平成9年(1997)、河川法は改正され、河川環境の整備、樹林帯、氾濫原の重視、水系ごとの河川整備計画への住民公聴会の設置、水利用の調整などが盛り込まれた。
平成7年(1995)6月には、形ばかりのものではあったが「ダム等大型事業審議委員令」が設置され、計画決定以来すでに長い時間が経過しているダム・大型治水事業の見直しのポーズもみせた。
こうしてみると、河川行政は少しずつ環境への配慮や事業への住民の参加を認めるほうへと歩みつつあるかにみえる。
しかし、治水計画については、住民を排除した密室でつくられた何年確率による基本高水を治水基準とするという体制はいささかも再検討の動きを見せていない。
|
(三) |
この治水計画における基本高水とは、そもそも何ものであろうか。
基本高水は昭和32年(1957)に建設省(当時)の定めた「河川砂防技術基準(案)」でとりあげられているもので、流域のある基準点で、治水計画の対処すべき最大の洪水流量を想定したものである。その算定法については特別に定めはない。そこで、現実には基準地点での集水域の降雨規模、降雨パターン、総雨量と降雨継続時間等、過去のデータからの引き延ばしや外挿による予測値を含む値から定めており、科学的に根拠のあるものではない。だから、いくつかの治水計画では、すでに予想した基本高水と現実の流出量との間に大きな違いがあったことが実証されている。以下、その若干を示してみる。
(a)千歳川放水路計画 基本高水(150年確率) 降水量:260mm/3d 1万8000m3/s 実際(1981) 282mm/3d 1万2000m3/s (b)吉野川可動堰計画 基本高水(150年確率) 降水量:329mm 2万4000m3/s 実際 578mm 1万1000m3/s (c)下諏訪ダム計画 基本高水 降水量:247mm/2d 280m3/s 実際(1999) 244mm/2d 140m3/sなぜこのようなことが起こるのかといえば、ダム等大型治水事業を予定した治水計画では、事業そのものを遂行するために、いくつかの予測値のうち最大のものを選択しているからである。過去の洪水流出体験から基本高水の想定が高すぎるということは、多くの治水計画地の住民運動の側からは指摘されてきたが、行政側は想定値は科学的根拠に基づく妥当なものとの態度を固持してきたのである。
|
(四) |
しかし、ある河川の治水計画にとって、どの程度の確率による洪水量を計画水量とするかは、流域住民とその管理を行う行政が対等の立場で検討し、決定すべきものである。また、ある河川にどんな治水・利水構造物を建設・設置すべきかという問題は、その河川の流域住民のみならず、その河川に関心を持つ幅広い人々の意見が集約されなければならない。なぜなら、河川は役所のものでも流域住民だくのものでもなく、いわば国民の財産であり、かつ治水・利水構造物は国民の税によってつくられるものであるからだ。
ところが、こうした民主的な河川行政のあり方からみると、これを阻止していたものは明らかに「河川法」であり、「構造令」であり、「砂防技術基準」であった。この中で、「河川法」は環境保護への関心の高まりや行政への住民参加の要求に多少なりとも応えて、幾分の改正は行われたが、旧河川法に基づく「構造令」や「砂防技術基準」はそのままである。
しかし、時代は明らかに河川行政に対して、より大きな環境重視と、行政への一層の住民参加を求めているといえる。それからすれば、もはや官主導密室による、何年確率の基本高水に基づく治水計画策定といったやり方は廃止すべきものといえる。
なぜなら、治水計画をどのくらいの洪水流量に対するものとすべきかは、行政と、技術者と流域住民が対等の立場で、過去の実測値と流域の現況等に基づいて検討し決定すべきものであるからだ。
その上で、これまでの徒に巨大な治水・利水施設はとりやめ、治水費のかなりの部分は、よりきめ細かな観測値をつかみ得るように観測体制の強化に向けるべきである。
このことは、巨大な治水・利水施設の環境破壊の大きさや、それが損傷した場合の被害の大きさから当然考えられなければならず、また最近の、従来のパターンと大きく異なる地域的集中豪雨の激しさからもいえるところであろう。
それにしても、本年(平成16年)9月8日の、国交省関東地方整備局の大西亘河川調査官による、長野県独自の流量観測に着いての「5年間だけでの観測で何が分かるか」という発言はいただけない。それなら、これまでのダム等大型治水計画における「高すぎる基本高水」に対する批判に、どれだけの観測実績によって説得的に応ずることができるというのか。それを公務員の当然の義務として明らかにしていただきたい。
こうしてみると、私たちの河川行政の改革を求める運動は、いまや密室で算定された基本高水に基づく治水計画を破棄し、河川行政の一層の民主化を求めて、脱ダムの向こうへ踏み出さなければならないといえよう。
(2004年12月)
このページの頭に戻ります
前ページに戻ります
[トップページ] [全国自然保護連合とは] [加盟団体一覧] [報告・主張] [リンク] [決議・意見書] [出版物] [自然通信]