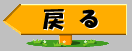■講演要旨
原子力は地球温暖化を救わない
グリーンピース・ジャパン 鈴木 真奈美
全国自然保護連合は(2008年)11月8日、総会と講演会を東京都内で開きました。
講演会では、グリーンピース・ジャパンの鈴木真奈美さんが「原子力は地球温暖化を救わない」というテーマで話をしました。
日本政府は、温暖化対策の目玉として原発推進をうたっています。しかし、これは温暖化対策の逆行するものです。たとえば、原発を1基建設すれば、そのバックアップ施設として火力発電所を1基つくらなければならないからです。また、京都議定書以降、日本は温室効果ガス排出量を8%も増やしています。これは、ヨーロッパ諸国が自然エネルギーへの積極転換などで排出量を確実に減らしていることと対照的です。
そこで日本は、海外からの排出権購入を当初予定の7000万トンから1億2000万トンへ倍増させることで、京都議定書第一約束期間における自主目標を達成しようとしています。その金額は数千億にのぼるとみられています。
これが「原発推進による温暖化対策」の実態です。これでは温室効果ガス排出量は絶対に減らせません。“原子力は地球温暖化を救わない”のです。
以下は、鈴木真奈美さんの講演要旨です。
|
鈴木真奈美さんの講演要旨 |
■原発に頼ったら二酸化炭素排出削減は困難
2007年7月に発生した中越沖地震は、東京電力の柏崎・刈羽原発を直撃し、同サイトにある全7基が運転を停止した。東京電力は同原発の停止による電力不足分は火力の発電を増やすことで対応している。
以前にも、たとえば東京電力のいくつかの原子力発電所で発覚した不正行為をきっかけに、2002年から2003年にかけて同社の原発全17基が順次運転を停止した。
また2004年には、関西電力の美浜原発3号機が蒸気噴出事故を起こしたことから、同社の他の原発8基も点検のため運転を停止した。これらによる温室効果ガス排出量の増加分は、2003年度は4.8%、2004年度は2.8%と計算される。
このように、原子力は常に巨大事故のリスクを抱えているため、いずれかの原子炉で事故やトラブルが生じると、同じモデルの炉や同じ事業者の炉を一斉に停止し点検する必要がでてくる。
そのため、原発が運転を停止するたびに、バックアップ用の火力発電所の発電量が増し、二酸化炭素の排出量はいきおい増大する。原発に頼っていたのでは、二酸化炭素の確実な排出削減は困難である。
■原発を増やすと電力需要が拡大する
原発の運転は100%かゼロのどちらかである。出力を調整できないので一日を通して常時使われる、いわゆる「ベースロード」電力しか供給できない。
需要が大きくなる時間帯の電力は、主に火力発電所が対応している。原発による「ベースロード」供給はすでにほぼ目いっぱいであり、電力需要の大幅な拡大なしには原発を今以上に増やすのは不可能である。
そこで電力会社は、オール電化住宅をはじめ、電力販売量を高めるキャンペーンを展開している。
しかし、電力需要が拡大すれば電力供給が全体的に増えるため、火力発電所による発電量も増大し、二酸化炭素の排出量も増える。
実際、1990年からこれまでに原発は18基増設され、原子力による発電量は増えたが、火力発電所も増設され、それによる発電量も伸び続けている。
とりわけ石炭火力による発電量と、それにともなう温室効果ガスの排出量の増加は著しく、2006年度はそれぞれ90年比の3.4倍と2.6倍だった。
■石炭消費量は京都議定書採択後も急増
日本が京都議定書の第一約束期間(2008〜2012年、日本は2008年4月1日より開始)で義務づけられている温室効果ガスの削減量は、1990年比で6%である。
温室効果ガスのうち、温暖化に及ぼす影響が大きいのが二酸化炭素である。
その主な発生源はエネルギー利用のための化石燃料の燃焼で、なかでも石炭は単位発電量当たりの二酸化炭素の排出量が大きいことから、その消費量を減らすことが削減目標の達成において重要な鍵となる。
ところが、日本の石炭消費量は増え続け、しかも温室効果ガスの削減を国際社会の目標とする京都議定書の採択後に急増している。
日本は現在55基もの原発を抱えている。同時に、世界の石炭貿易量の4分の1を占める最大輸入国でもある。
■エネルギー転換にとりくまない
問題は、こうした転換を促すような政策を、日本政府が示していないことである。
90年代半ば以降、電力事業の一部自由化にともなう競争の激化と石油価格の高騰から、電力会社や新たに発電ビジネスに参入した事業者は、値段と課税率が比較的低い石炭の利用を増やしている。
石炭が課税対象になったのは2003年で、それまでは非課税だった。課税後も税率が低く、発電や熱供給の事業者に石炭を選択するインセンティヴを与えている。 実際、発電電力量に占める石炭火力の割合は、1990年におよそ10%だったのが2005年には25%を上回った。
その結果、二酸化炭素の直接排出量における発電部門の割合が増え、約30%を占めるほどになっている。
発電部門の排出量を減らすには、石炭火力への依存を減らしていかなければならない。ところが日本では、今後10年間で新たに5基の石炭火力発電所の運転が計画されるなど、逆に増える方向にある。
日本政府や電気事業者は、発電部門からの排出は、石炭火力のエネルギー効率を向上させたり、原子力の割合を増やしたりすることで低減を図るとしている。
しかし、現在の最新の石炭火力技術を導入しても、従来型より5%低減できるだけである。2020年から30年頃の実用化をめざして開発が進められている新技術(石炭ガス化複合発電等)にしても、その削減効果は20%ほどだから、単位発熱量あたりの排出量が石油火力と同程度になるのがやっとである。
■自然エネルギーを増やす制度導入が必要
石炭火力による発電量の増大が、二酸化炭素排出量を高める大きな要因となっているのだから、この部分を是正していくような政策が必要である。
石炭の利用が経済的に高くつくような仕組み(たとえば石炭への課税率を高めたり、炭素税や環境税の導入など)を設けることなく、事業者の自主努力だけで石炭火力による発電量が減るとは考えられない。
当面は、石炭火力の設備利用率を低くして天然ガス火力のそれを高くするような措置をとること、そのうえで長期を見通した燃料転換を進めていくこと、そして自然エネルギーを増やすための制度をできるだけ早く導入することが、もっとも現実的で確実な削減効果が期待できる施策である。
■原子力では確実な削減は不可能
日本政府は原発の設備容量と設備制用率を高くすることを前提に、二酸化炭素の排出削減見込み量を算定している。
1998年の『地球温暖化対策推進大綱』では、2010年までに原子力による発電電力量を1997年比で5割増しにするとし、同年の『長期エネルギー需給見通し』には20基の原発増設が盛り込まれていた。
そのなかには70年代に計画された現在では通用しないようなモデルの原発まで含まれている。
いずれにせよ、住民の反対だけでなく、前述のように電力の需給バランスからも、これ以上の増設は困難である。
■既設原発の稼働率引き上げで削減目標達成をめざす
原発の増設が難しいことから、その後に策定された『京都議定書目標達成計画』(2007年)では、既設原発の平均設備利用率を最大88%まで引き上げることで、削減目標を達成しようとした。
しかし現実には、事故や不祥事のために、2003年度は59.7%、2004年度は68.9%、柏崎刈羽原発や志賀原発による計画外停止が相次いだ2007年度は60.7%と、低迷がつづいている。
日本政府は設備利用率を高めるため、原発の定期点検の間隔を長くし、連続運転日数を現在の13カ月以内から最長24カ月まで延長する方針である。
■安全犠牲の方策に地元から反対の声
しかし、現在稼動している原子炉は2015年までにその半数以上が、2025年までにそのほとんどが運転年数30年を超え、老朽化による機器や金属、コンクリートなどの劣化は避けられない。
経年劣化による事故を防ぐには、より厳密な定期点検が不可欠である。設備利用率を高めることで老朽化が進む原子炉の負担を増大させるのは、「原子力災害」のリスクを高めることにもつながりかねない。
こうした安全を犠牲にした方策に対し、原発を抱える地元から反対の声があがっている。
■大金を投じて国外から排出権を買いつづけることに
非現実的な原発増設計画と設備利用率を想定した削減計画は、もとより達成不可能だったのは明らかである。
電力会社は、京都議定書第一約束期間における自主目標を達成できそうもないため、海外からの排出権購入を、当初予定の7000万トンから1億2000万トンへほぼ倍増するとしている。
炭素価格は変動するので、最終的にどれほどの額になるかは定かではないが、数千億にのぼるだろう、との見方もある。
不安定な原発に削減対策を頼っていたのでは、大金(すなわち、私たちが支払う電力料金)を投じて、国外から排出権を買いつづけることにもなりかねない。
こうしたやり方は、本来の削減策からは程遠い対処療法である。資金を燃料転換や自然エネルギーの導入といった国内対策に向ければ国内での削減に効果があるだけでなく、雇用の促進や経済効果も期待できると思われる。
■省エネとエネルギー効率向上が求められている
エネルギー利用のあり方を見直す国際エネルギー機関(IEA)や日本の国立環境研究所などによる報告書が結論づけているように、温室効果ガスを削減するうえで、もっとも効果的な施策は省エネとエネルギー効率の向上である。
発電に投入される一次エネルギーは、無駄になっている割合が高いことから、温暖化対策にとって、この部門における効率向上がきわめて重要となる。
なかでも原子力発電はエネルギー効率がよくない。その発電効率は35%を超えることはなく、残りは廃熱となる(熱のほとんどは温排水として海に捨てられているため、海洋生態系や漁業への影響が問題視されている)。
さらに原発の場合、電力の大消費地から遠く離れた場所に立地せざるをえないため、約8%が送電中にロスとして捨てられている。
原発ではこうしたロス、すなわちエネルギーの「無駄遣い」が避けられない。
原発に代表される大規模集中型発電システムにたいし、分散型エネルギー供給システムの場合、必要なエネルギーを需要のある場所でつくり、そこで消費(エネルギーを「地産・地消」)するため、送電ロスを小さくできる。
さらにコジェネレーションを導入し、排熱を冷暖房・給湯・蒸気などに有効利用すると、総合エネルギー効率は80%以上に向上するとされ、燃料(一次エネルギー)の供給量と二酸化炭素排出の削減が可能となる。
たとえばデンマークでは、電力の50%、地域熱供給の80%が、すでにコジェネレーションでまかなわれている。
このように、分散型エネルギーシステムとコジェネレーションを組み合わせれば、電力需要が現状を維持したとしても、電力部門の燃料(一次エネルギー)の供給量(すなわち石炭や石油、天然ガスといった一次エネルギーの投入量)を大きく減らすことがでる。また、熱供給のためのエネルギー消費も減らすことにつながる。
■持続可能なエネルギー供給と安全を保障すること
原子力発電は、大量のロスを見込んで大量に電気をつくり、大量に消費し、そして大量の放射性廃棄物を生み出すシステムである。
かつては、エネルギー需要の増大が「豊かさ」の指標とされ、エネルギー政策の重点は燃料を確保し、安定供給することにおかれていた。
しかし気候変動の脅威が迫りつつあるいま、世界の、とくに先進国の政策に求められているのは、原子力発電に代表されるエネルギー利用のあり方を見直し、現在と将来の世代にたいし、持続可能なエネルギー供給と安全を保障することである。
グリーンピースは持続可能なエネルギー・シナリオ──エネルギー[r]eボリューション──を、ドイツ航空宇宙センターや各国の研究者の協力を得て作成した。
日本シナリオは2030年までに自然エネルギーで電力需要の32%を、2050年までに61%をまかなうことが、技術的に可能であることを示している。自然エネルギーはすでに実証された技術であり、その導入と普及は政策の問題である。
■日本だけがプルトニウム利用に固執
日本政府は、原子力を導入した当初から、その拡大を国策と位置づけ、原発や核燃料サイクル施設の立地を進めてきた。
そして、パブリック・アクセプタンス(PA:社会的容認)活動や、さらには電力会社が原発導入によって被る経済的リスクまで、税金で負担してきた。
2006年に公表した『原子力立国計画』と2007年3月に改定した『エネルギー基本計画』では、これまで以上の積極的な支援策が示されている。
たとえば電気事業制度の改革が審議されているが、電力自由化を検討するにあたっては、「今後の原子力発電投資に及ぼす影響に十分に配慮して慎重な議論が行われることが適切」とするなど、原子力に偏重した政策が目立つ。
これは政府予算によくあらわれている。
2004年度を例にとると、エネルギー研究開発予算のうち約64%が原子力に投じられ、自然エネルギー(日本政府はこれを「新エネルギー」と呼びます)へは、わずか8%だった。
日本のエネルギー研究開発予算の額は世界−で、2004年度は米国の3倍、ドイツの10倍である。しかしその大部分が原子力、それも高速増殖炉開発にあてられている。
後述するが、高速増殖炉は危険な気候変動を回避するうえで、なんら貢献しない。
ちなみに日本政府の2008年度予算では、高速増殖炉は「京都議定書の削減約束に中長期的に効果があるもの」として、また原発立地地域への交付金は「6%削減に直接効果があるもの」として、大きな額が投じられている。
交付金が「6%削減」にどのように「直接」貢献するのか、はなはだ疑問である。
こうした原子力にたいする過度の優遇策は、エネルギー計画の柔軟性を奪い、エネルギー市場を歪め、省エネ技術の発展や自然エネルギー、分散型システムの導入など、本来、地球温暖化対策の主柱となるべき分野の開発と導入を阻害している。
ウランも化石燃料と同様、有限の資源である。そこで原子力発電を導入した国々は、当初、使用済み核燃料を再処理してプルトニウムを取り出し、それを高速増殖炉の燃料として利用する計画だった。
高速増殖炉のなかでは、理論上、燃料に使った以上のプルトニウムが生成される。
これにより核分裂エネルギーを何千年間も利用できるとの喧伝がなされてきたのである。
しかし、ほとんどの国が、プルトニウムを燃料に使う「再処理─高速増殖炉」路線から撤退した。コスト、放射能汚染、放射性廃棄物、プルトニウムの拡散リスク等々の負担が、ウラン燃料とは比較にならないほど大きくなるためである。
そして、永久に使えるエネルギー源として、自然エネルギーを推進する国々が増えている。
ところが日本だけは、プルトニウム路線を国のエネルギー政策と地球温暖化対策の要に据え、その開発に巨額の国家予算を投じ続けている。
■非現実的な技術開発に貴重な時間と巨額の税金を
投入している余裕は残されていない
とはいえ、日本政府の見通しでも、高速増殖炉サイクルが「実用化」されるのは2050年である。
温暖化対策は時間との競争である。1基かそこらが「実用化」されても電力の主要供給源にならない。ましてや、危険な気候変勤を回避するうえで、なんの効果も期待できない。
高速増殖炉サイクルが現行の軽水炉サイクルに取って代わるには、プルトニウムが増殖し、さらに40基あまりの高速増殖炉と、それ専用の再処理工場やその他の施設が必要となる。
これが可能となるのは、早くて来世紀とされている。そもそも、プルトニウムの有効な増殖が可能かどうかさえ未知数のままである。増殖が見込めなければプルトニウムは「無尽蔵のエネルギー」源にはなりえない。
核融合エネルギー発電も同様である。人類が核融合エネルギーを得るには、重水素(D)と三重水素(T)が反応する「D−T反応」を利用するしかない。しかし、この反応で発生する強烈な中性子に長く耐えうる資材は、今のところ、地球上には存在しない。
また核融合は、三重水素などで汚染された大量の放射性廃棄物を生み出す。可視的な将来においで、商業規模の核融合炉を建設するのは不可能であるし、核融合エネルギーが主要な電力源になることもありえない。
つまるところ、核融合で巨大なエネルギーを生みだせるとしたら、熱核兵器の爆発だけである。
近年、気候変動抑止における原子力発電の有効性をめぐり、世界中で議論が続いている。
しかしプルトニウム利用(すなわち再処理と高速増殖炉)や核融合は、具体的な対策として議題にさえのぼっていない。
核融合炉はもとより高速増殖炉にしても、その実用化は机上の計画にすぎず、100年以上たっても実現可能かどうかさえ定かでない「夢の原子炉」では、喫緊を要する地球温暖化対策になりえないからである。
このような非現実的な技術の開発に、貴重な時間と巨額の税金を投入している余裕は、もはや残されていない。
■今後10年間に原子力が果たせる役割はない
国際エネルギー機関(IEA)の『エネルギー技術展望2008』は、2050年までに世界の二酸化炭素の排出量を半減するシナリオ(「BLUEシナリオ」)のなかで、これを原子力の増大によって達成するには、その発電量を現在の4倍に増やすことが必要だとしている。
それには100万キロワット級の原発が、年間32基、つまり毎月2.6基が、送電を開始しなければならない。
建設だけでなく実際に送電できるようにするには、現実的な判断にたてばおよそ不可能である。たとえ達成できたとしても、IEAの見通しでは、発電部門における削減効果は6%にすぎない。
ここで重要なのは、原子力発電は原子炉だけあっても機能しないということである。
ウラン濃縮工場、燃料加工工場、放射性廃棄物貯蔵施設、最終処分場、選択によっては再処理工場やプルトニウム貯蔵施設、プルトニウム燃料加工施設などの一連の核施設も増やす必要がある。
これらにかかるコストと時間は、たとえば原子炉だけをとってみても、そのコスト(1基あたり数千億円)、設置計画から操業までに要する時間(ほとんどのケースで10年以上)、国によっては高圧送電線をはじめとするインフラの基盤整備や核拡散防止措置の強化など、膨大なものとなることが予想される。
また、事故や放射能汚染、そして核拡散やテロの危険性をはじめとする原子力特有のリスクが高まる。
いずれにせよ、二酸化炭素の排出量を減少へと転じなければならないこの決定的な10年間ほどのうちに、原子力が果たせる役割はない。
■政府は原子力技術の輸出を計画
2005年に国際原子力機関(IAEA)が実施した世論調査によると、日本国民の76%が原発の増設に反対している。
2007年7月の中越沖地震以降、世論は原子力に対しますます厳しくなっており、また前述のように電力需給バランスからみても、これ以上の増設は難しい。
そのため、日本の原子力産業は、ビジネスと技術の維持のために、アジアや米国などへ原子力技術を輸出しようと計画し、日本政府も「地球温暖化対策につながる」として、それを積極的に後押ししている。
京都議定書は、海外で実施した事業による排出削減量を投資国の削減実績とみなす仕組みを設けた。そのひとつが「クリーン開発メカニズム(CDM)」である。
ただし、原子力発電はその対象にはなっていない。日本政府は、次期の枠組みで原子力をCDMに加えるよう働きかけを強化する方針である。
■世界のNGOは日本政府に不名誉な「化石賞」を授けた
日本政府のこの動きにたいし、世界のNGOは、2007年にインドネシアのバリで開催された気候変動枠組条約第13回締約国会合(COP13)において、不名誉な「化石賞」を授けた。
国際協力銀行や日本貿易保険は、これまで対象としていなかった原発輸出を、それも先進国向けもカバーする方向で修正を進めている(2008年6月現在)。金融支援を通じて、原子力産業が海外に進出しやすい環境をつくろうとしているのである。
しかし、原子力技術移転は、非効率的なエネルギーシステムを輸出することにほかならない。原子力はその特性から、数十年先まで見据えた立案が不可欠なため、原発を盛り込んだエネルギー政策がスタートしてしまうと、その見直しが難しくなり、エネルギー多消費型の社会が築かれていく。
これは、日本をはじめ原発先進国が経験してきたことである。また、前述のように、出力調整用やバックアップ用電源として、火力発電所も確実に増える。
■日本が世界に普及すべきはエネルギー効率利用向上技術
日本が技術移転を通じて世界に普及すべきは、自然エネルギーを中心とする分散型エネルギーシステムやエネルギーの効率利用を向上させる技術である。
(文責・『全国自然通信』編集部)
このページの頭に戻ります
前ページに戻ります
[トップページ] [全国自然保護連合とは] [加盟団体一覧] [報告・主張] [リンク] [決議・意見書] [出版物] [自然通信]